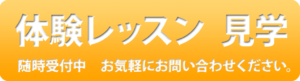社会におけるピアノの位置付け、の歴史
ピアノほど有名で、多くの人が演奏する楽器はなかなかないと思います。そのピアノって、どうやってこんなに広まったのか、不思議になったので調べてみました。
英語版ウィキペディアの記事「Social History of the Piano」によると、1709年にイタリアの楽器職人バルトロメオ・クリストフォリによってピアノが発明された直後は、ピアノはとても高価なもので一部の貴族にしか触れない楽器でした。当初は前身のチェンバロが主流で、世間に受け入れられるまで時間がかかったようですが、19世紀になるとやがてピアノは富の証として特に中流階級の憧れの的になったそうで、女性はピアノが弾けると良い縁談に恵まれるというという位置付けもあったそうです。
面白いことに、遠い日本でピアノが知れ渡り始めた明治維新後にも貴族の間には同じような発想が生まれたようで、「貴族の娘ならピアノくらい弾けないと」ということで多くの人たちがピアノを習ったと「日本のピアノ100年: ピアノづくりに賭けた人々」という本に書かれています。
いずれにしても、ピアノ音楽にはそのように可憐で上品で…とか、高級感のある印象があったのでしょうね。
欧米では、ラジオやレコードの登場とともにピアノの生産・販売台数は減っていきます。一生懸命練習しなくても音楽を楽しめるようになったから。この後多くのミュージシャンが職を失ったのだろうな、と想像します。
日本はまた特殊で、第二次大戦後の高度経済成長の恩恵で、子供の頃ピアノに憧れつつも手が届かなかった娘さんたちが母親になった頃、我が子にはピアノをさせたいという自分の夢を子供に託すみたいな現象が起こり爆発的にピアノが売れます。昭和50年代半ばくらいまでがピークでした。
ピアノはいつの時代も人々の憧れで、ピアノを弾ける人ってすごい!というのが古今東西共通のイメージでした。
ピアノって、こんなにも長く親しまれ憧れの的になり続けられて偉大だな、と思います。